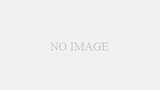寒中見舞いのはがきを
出そうと思ったものの、
「いつからいつまで送れるの?」
「年賀状の代わりになる?」など、
意外とマナーが気になりますよね。
本記事では、
寒中見舞いを送るタイミングや
使える場面・正しい書き方まで
わかりやすく解説します。
2025年版の最新マナーに
合わせた文例も載せていますので、
ぜひ参考にしてみてくださいね。
寒中見舞いの時期は「松の内明け」から
寒中見舞いは、
「寒さが厳しい時期に相手を気づかう」
という意味があります。
だからこそ、送るのは
寒さが本格化するタイミングが
マナーとされています。
→ 1月8日〜2月3日(立春前日まで)
年賀状は松の内(1月7日頃)までが目安ですが、
寒中見舞いはそのあとから出すのが一般的です。
松の内の時期に注意
実は「松の内」は
地域によって終わる日が異なります。
| 地域 | 松の内の終わり |
| 関東 | 1月7日 |
| 関西 | 1月15日 |
たとえば関西の方に出すなら、
1月16日以降が安心ですね。
寒中見舞いを送る意味とは?
寒中見舞いには、季節のご挨拶とともに
さまざまな「伝えたい気持ち」を込めることができます。
✔ 年賀状の返事が遅れてしまったお詫び
✔ 喪中の方へのご挨拶として
✔ お歳暮や年賀の品物へのお礼
✔ 病気や災害に遭った方へのお見舞い
✔ 寒さの中での気づかいの気持ち
形式にとらわれすぎず、
思いやりを伝えることが大切です。
寒中見舞いってどんなときに送るの?
寒中見舞いは、
ただの「季節のご挨拶」だけでなく、
実は使える場面が
意外とたくさんあります。
✔ 年賀状の返事が遅れたとき
うっかり年賀状を出しそびれた相手へ
遅れて寒中見舞いを送るのはOKです。
✔ 喪中の方へのご挨拶
喪中の相手には年賀状を避けるのがマナーですが、
寒中見舞いなら送っても問題ありません。
✔ 喪中はがきへの返礼
いただいた喪中はがきへのお返しにも
寒中見舞いがよく使われます。
✔ お歳暮・お年賀のお礼に
品物をいただいた場合の御礼状として
寒中見舞いを活用する方も多いです。
寒中見舞いの文面はどう書けばいい?
文面には、基本の流れがあります。
相手との関係に合わせて、
言葉を選ぶとより丁寧です。
✔ 挨拶文は「寒中お見舞い申し上げます」
年賀状のような「謹賀新年」などは使いません。
✔ 寒さをいたわる一言を添える
「厳しい寒さが続いておりますが…」などが定番です。
✔ 近況報告やお詫び、お礼を加える
必要に応じて加えましょう。例:「年始のご挨拶が遅れ…」
✔ 最後は相手の健康を気づかう
「どうぞご自愛ください」などで締めます。
寒中見舞いのはがき、どれを使う?
年賀はがきの余りはNG!
寒中見舞いには、
私製はがきまたは通常はがきを使いましょう。
デザインは、
雪・梅・椿など冬〜早春を感じさせるもの
が好印象です。
喪中の相手には、
派手すぎない落ち着いた色や図柄が安心です。
よくあるQ&A
Q. LINEやメールで送ってもいい?
最近は、カジュアルな関係なら
SNSやメール、LINEでのご挨拶もOKです。
ただし、
目上の方や正式な相手にははがきがベター。
シーンに応じて使い分けましょう。
Q. 寒中見舞いの時期を過ぎたら?
2月4日以降は「余寒見舞い」に切り替える
のがマナーです。
「寒さ厳しき折から~」などの表現に変えましょう。
Q. 地域によって送る時期を変えるべき?
はい、少し配慮できると丁寧です。
例えば、
関東なら1月8日〜2月3日、
関西なら1月16日〜2月3日が目安です。
まとめ
寒中見舞いは、冬のご挨拶として
相手への気遣いを届ける素敵な文化です。
年賀状が出せなかったときや、
喪中の相手に配慮したいときなど、
状況に応じて活用できるのも魅力です。
「もう遅いかな…」と思っても、
余寒見舞いという方法で気持ちは届けられます。
この冬、大切な人に
あたたかいメッセージを届けてみてはいかがでしょうか。